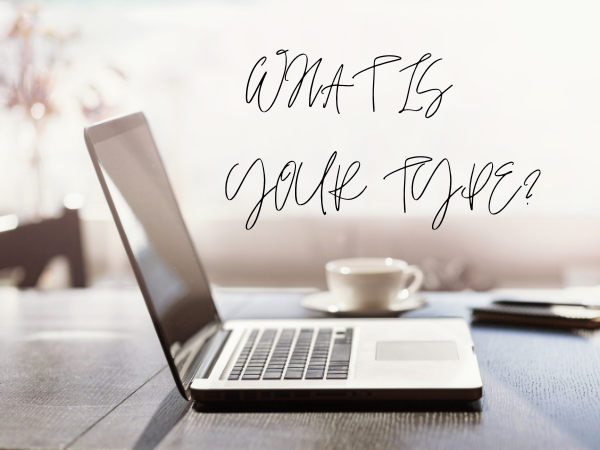【2022年下半期から2023年上半期のお仕事について】
昨年下半期は、比較的長丁場の仕事が重なりました。
自己診断・マッチング・心理テストに関する
ご依頼の比重は、例年とほとんど変わらず、
診断コンテンツの制作をしながら、他方で
心理テストの新しいアイデア出しをしている日々。
それと並行して講座・セミナーを開催しています。
ご依頼いただいた主なジャンルは:
①診断コンテンツ
・大手人材・マッチング系企業
会員向けサイト
・美容関係
②心理テスト 連載 Webサイト
③イエスノー診断チャート イベント仕様
・放送局大イベント
・ショッピングモール季節イベント(バレンタインデー)
・ファッション関係
④会員誌 自己診断ページ
⑤監修 子供向け単行本(心理テスト)の監修
⑥ゲームキャラ 日本語解説
※自己診断・人材マッチング系サービスでの診断コンテンツは、
会員のみ閲覧可能なサイトに設置されることが多くなり、
具体例を挙げることがむずかしくなっております。
各企業様、それぞれ、独自の観点から、展開しておられます。
【診断コンテンツはAIで簡単に作れるのでは?】
AIの発展で、近年、診断コンテンツや
心理テストなども、AIで制作出来ますという
サイトの文言を目にするようになりました。
ユーザーの関心を引き、SNSに紐づけるところでは、
ある程度、宣伝効果があるかもしれません。
ただ、AIで人の心理を診断することのデメリットも
あると思っています。
最近では各サポート窓口の電話対応なども、
AIでの案内がほとんどといっていいほどです。
AIを導入することは人員削減、コストダウンにも
つながるのでしょう。
ネットでの対応もチャットボットが一般的に
なりました。
しかし、自分がユーザーとして、それを
利用する際の心理について想像してみてください。
イライラしたことはありませんか?
聞きたいことが選択肢に入っていない。
だから、どちらかを選べと言われても選べない。
その際、どうすればいいのか。イライラ。
聞きたいことがちょっと込み入っている。
その選択肢がない。イライラ。
最初はサクサクと答えていけたけれど、結局
その質問に対しては「次のサイトを閲覧ください」とか、
「メールで問い合わせを受け付けています」とか。
いちばん親切なケースでは、
「電話受付サポートにおつなぎます」と、
よ・う・や・く、人の声が聴こえるサポート窓口に
つないでくれる。
ユーザーはそれまでにイライラしているので、
生の声が聴こえてくると、当てつけの一つも
いいたくなる。担当者、ストレスがたまる。
で、対策。やっぱり、サポート窓口は
すべてAIにしたほうがいいという結論に(笑)。
【診断コンテンツもAI でほぼ出来上がる?】
さて、そこで性格分析や自己診断コンテンツ、
またそこから適職、相性診断やマッチングに
つなげていく場合はどうでしょうか。
それはできるでしょうし、実際やっているところも
あるかと思います。
ただ、人の心理を扱うものである以上、
ユーザーにストレスを与えるようなものであってはいけない。
というのは、大前提ですね。
イエス・ノーの二択では、もちろんどちらかを
選ばなければならないわけですが、
そのときの言い回しにも配慮が必要です。
もっとも、これはAIでも設定できなくはないでしょう。
ただ、設問の言葉の一語一語には人の目が通っている。
そこで、その問いが適切かどうかを判断します。
診断・解説における言葉の一語一語、
ユーザーがどのような受け止め方をするか、
言葉のニュアンスはどうか、工夫が必要なこともあります。
NGワードは当然のことながら、言葉上は問題がなくても、
使用しない方がいい単語などもあります。
刻々と変化する時代の価値観や人による受け止め方なども、
考慮に入れておかなければなりません。
また、診断コンテンツをどのような目的で設置するのか。
適職診断なのか、恋愛心理なのか、
結婚を前提としたマッチング診断なのか、
どのような企業イメージをもち、
どのような商品を扱う商品相性診断なのか、
子供向けの心理テストなのか、
言葉の選び方は全部違ってきます。
筆者がご依頼を受けたクライアントもしくは
制作会社の担当の方と何度もやり取りをします。
場合によっては、ニュアンス的な問題で
全面作り直しのような作業も必要になることも
あります。
できるかぎり、ご依頼主の目的、イメージ、意図に
沿った形で、ご満足のいただける制作物を仕上げる
ようにしています。
手をかけるほど、おそらくユーザーの反応も
よいものが仕上がることをお約束できます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、次回は診断コンテンツ制作と並行して
筆者が行っておりますエニアグラムの講座やセミナー、
個人セッションに参加された新卒生の、
エニアグラム活用による、就職活動での成功例について、
ご本人からいただいたレポートをご紹介いたします。