AI時代における「心理テスト」の価値とは
――MBTIブームのあとに考える、エニアグラムと診断コンテンツの可能性
10月も半ばとなりました。
今年の前半には「MBTI」がずいぶん流行していましたが、最近は少し落ち着いたように感じます。
私が長年メインに研究してきたのは「エニアグラム」という性格モデルです。単なるタイプ分けではなく、人間の内面構造や成長の方向性を示す――より深く、実践的な知恵を含んだ体系です。
そして私が企業や個人事業主の方と関わるときには、このエニアグラムをはじめとする「診断コンテンツ」をビジネスにどう活かすか、という観点が中心になります。これまでにも、雑誌やSNSキャンペーン、保険・化粧品・ファッション業界など、さまざまな分野で心理テストやチェックテスト/チャート式診断を制作してきました。
AIが心理テストを「作れる時代」になっても
最近はAIの進化が本当にめざましいですね。
「AIで心理テストは作れるのか?」という質問をよくいただきます。実際のところ、AIを使えば“それらしいもの”は作れます。私自身もテーマ設定や設問の整理、言い回しの調整などにはAIを活用しています。
けれども――結局のところ、AIが作るものは「データの再構成」に過ぎません。
心理テストや診断コンテンツの本質は、クリエイティブな部分にあります。
データを処理する力がいくらあっても、そこに「人の感情」「読者の体験」を織り込むことは、まだAIにはできないのです。
私がつくる心理テストは、研究室で使うような厳密な心理尺度とは違います。
読む人に“楽しみながら自分を知る”体験を提供する――いわば「心理ゲーム」に近いジャンルです。
読者の心に小さな気づきや笑顔が生まれる、そんな仕掛けづくりが重要なのです。
「心理テストは(お客様に)失礼」?――誤解から見える本質
以前、ある制作会社さんから心理テストの依頼をいただいたときのこと。
途中でクライアントから「心理テストはNGです。お客様に心理テストをするなんて失礼です」と言われたそうです。
そのとき私は思いました。
――ああ、「心理テスト」という言葉が誤解されているんだな、と。
私たちが扱う心理テストは、人の心の病理を浮かび上がらせるようなものではありません。
「あなたの魅力はここにあります」「こういう選び方が向いていますよ」といった、ポジティブで楽しい内容です。
読者が読んで心地よくなる。思わず「自分に当てはまるかも」と感じてしまう。
その体験こそが、心理テスト(ゲーム)の“価値”なんです。
心にフックを作る――心理テスト的アプローチの力
この「心に残る仕掛け」という意味で、心理テストやチェックチャートはとても強力です。
たとえば最近、地方で配られていたあるパンフレットを手に取ったのですが――正直、どれも似たように見えてしまって、記憶に残らなかったんです。
立派な言葉が並んでいても、読む側の心に“引っかかり”がない。
結局、最後まで読む気にならないんですね。
一方で、心理テスト的な構成――つまり「あなたはどのタイプ?」「はい・いいえ」で進むチャート式の構成――を入れるだけで、人は思わず立ち止まります。
なぜなら人は、商品よりも“自分”に興味があるからです。
選択肢を選びながら読み進めていくと、自然と「自分に関係ある内容だ」と感じる。
その結果、広告やチラシ、SNS投稿であっても、滞在時間が伸び、記憶にも残る。
それが“心理テストの力”なのです。
企業・ブランドが「心地よく響く」診断を使う理由
大手保険会社、化粧品メーカー、通販サイト――
私がこれまで制作した心理テストの多くは、こうした企業の広告や小冊子にも使われてきました。
内容はいずれもポジティブで、読者が“読んでよかった”と思えるもの。
「面白かった記事」として挙げてくださる方も多く、好評をいただいています。
特にチャート式やイエスノー式のテストは、
SNSでのクリック率向上
広告からの滞在時間アップ
ブランドへの親近感の醸成
といった点でも効果的です。
心理テストは、単なる遊びではなく、「共感」と「興味」を自然に引き出すコミュニケーションツールなのです。
おわりに
AI時代になっても、人の心を動かすのは「人の言葉」だと思います。
心理テストという形を通して、読者やお客様が自分自身を見つめ、
“ちょっと前向きな気持ち”になる――そんな体験を作り続けていきたいと思っています。
これからも、診断コンテンツをビジネスの現場でどう生かすか、
そしてAIとどう共存していくか、発信を続けていきます。

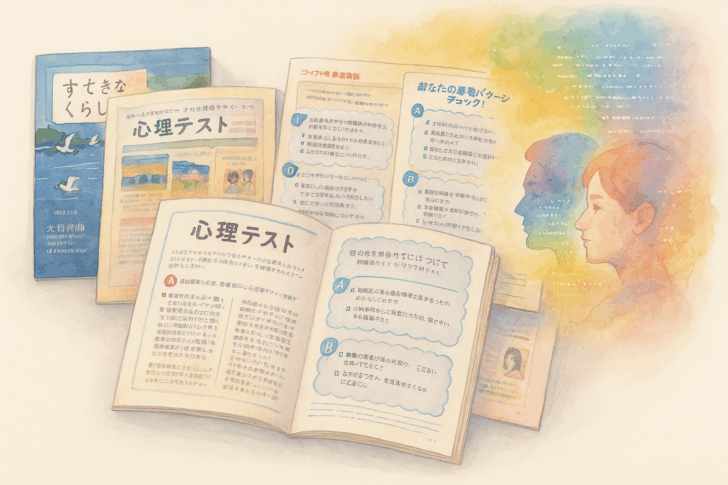














診断コンテンツは何故ユーザーに好まれるのか?
自社サイトへの集客がうまくいかない、なかなかサイトの成果が上がらない。 もしくは、商品・サービスの認知拡大をしたいが、方法が分からないと困っていませんか?
「診断コンテンツ」はそんなお悩みを解決できる手法です!
◉著書120万部のベストセラー実績! ◉性格診断・心理テスト ◉各種ニーズに紐づける診断チャート ◉ロジック制作・原稿執筆・監修 など多くのコンテンツ制作を行ってきた中嶋真澄が、 あなたのお悩みに寄り添います!